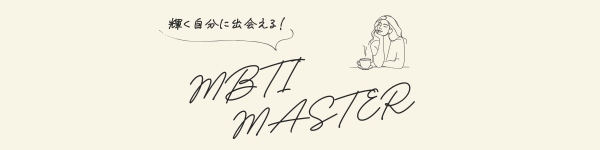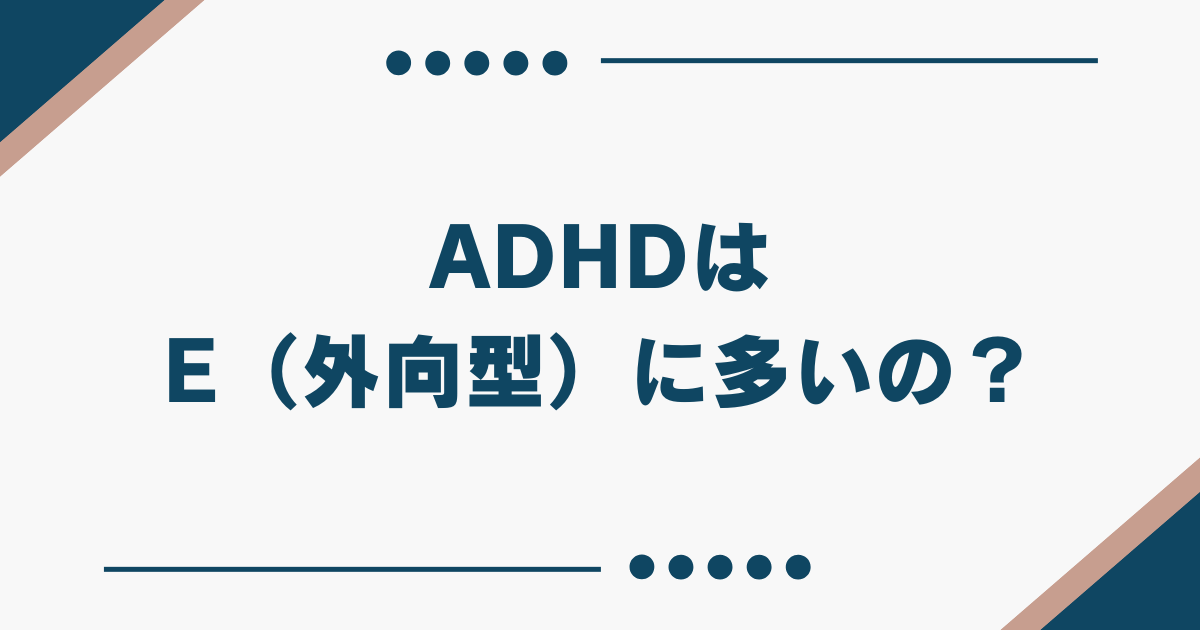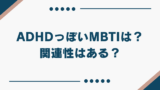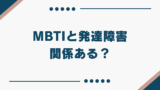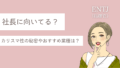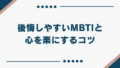外向的で、いつも動いてないと落ち着かない…
そんな自覚はありませんか?
もしかするとそれは、E(外向型)×ADHDっぽさが重なっているサインかもしれません。
実際、ADHD傾向をもつ人が MBTIのE(外向型)もしくはP(知覚型)と重なりやすく、外向型とADHDの関係性から自己分析をする人も増えています。
この記事では、なぜE(外向型)に ADHDっぽさが見られやすいのか、またどんなMBTIタイプが挙げられるのかを解説。
E(外向型)×ADHDっぽい性格を、ポジティブに活かす方法もご紹介します!
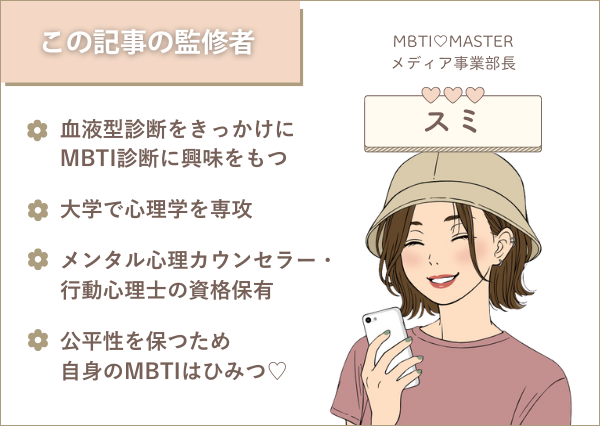
ADHDはE(外向型)に多いの?
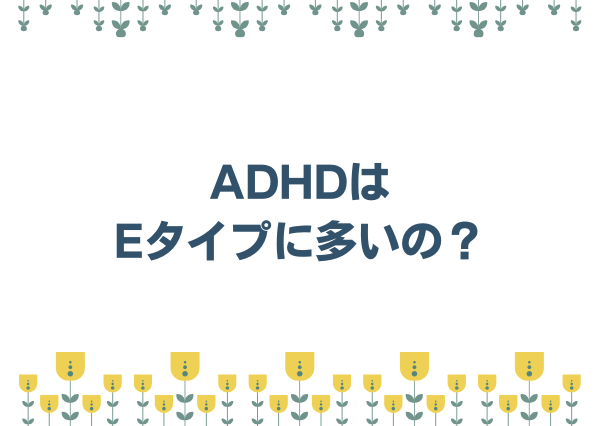
E(外向型)の人は、エネルギーを外に向ける傾向があります。
他人との交流・刺激・行動・体験を通じて活力を得るため、内側に溜め込むタイプと比べて動き・変化・反応が常にある状態を好むと考えられます。
ADHD(注意欠如多動症)の傾向としては、じっとしていられない・すぐ行動に移したくなる・集中力が続かない…といった特徴があります。
こういった特徴が、E(外向型)の人がもつADHDっぽさとして捉えられることがあるのです。
つまり、E(外向型)ならではのエネルギーの発散欲求と、ADHD特有の動きたくなる傾向が、似た行動パターンを生み出しやすいのですね。
E(外向型)は、場を盛り上げたり周囲のリアクションを見て安心したりする傾向があります。
刺激を求めて飽きっぽくなったり、雑多なアイデアが浮かびやすく、結果として注意散漫に見えたり、抜けている印象を持たれたりするのです。
【外向 × 多動】の視点から
E(外向型)は、外部の刺激から活力を得ます。
そのため、イベントや飲み会など、人との交流や動きのある環境を好みます。

この点が、ADHD的な「じっとできない」「すぐ動きたくなる」傾向と重なるのですね。
たとえば「常に何かやっていないと落ち着かない」「じっと話を聞くよりも身体を動かしていたい」という感覚を持つE(外向型)は、自分を「ADHDっぽいのかな?」と考えたことがあるかもしれません。
そのような性質により、E(外向型)がADHDの多動性と関連して見えるのでしょう。
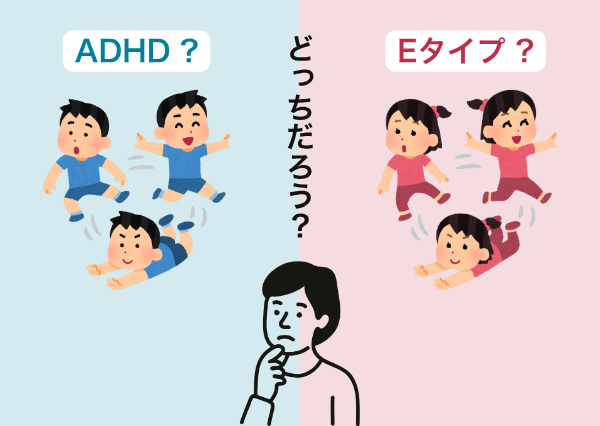
【外向 × 衝動】の視点から
ADHDの特徴に「衝動的に動いてしまう」「興味・関心が移ろいやすい」というものがあります。
E(外向型)の人もまた、アクティブでエネルギッシュなので「考える前に行動しがち」「1つのことを終わらせる前に次のことに取りかかる」というふうに見えるかもしれません。
そのエネルギッシュさが、周囲から「落ち着きがない」と捉えられてしまうのですね。

E(外向型)のエネルギッシュさもそうですが、これに加えてP(知覚型)をもったタイプだと、フットワークの軽さがさらに際立ちます。
P(知覚型)は計画を立てず即行動に移ったり、飽きっぽくマイペースであることが特徴なので、よりADHDっぽく見えるかもしれませんね。
【外向 × 継続性】の視点から
ADHDっぽさのもうひとつの側面は「集中が続かない」「ルーティンが苦手」というものです。
E(外向型)は外に意識が向くため、静かな作業やルーティンワーク、かわりばえしない環境が負荷になりやすい傾向があります。
このため、ADHDっぽさをもつE(外向型)は、チームで進める仕事はスムーズなのに、1人の作業になると手が止まってしまったり、ひらめきは豊富だけど最後まで続かなかったり…
そんなモヤモヤを感じることがあるでしょう。

ADHDっぽく見えるE(外向型)タイプとは
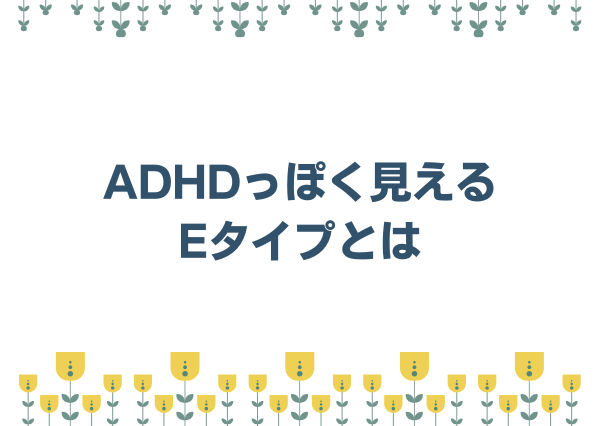
科学的な研究で「このタイプがADHDに多い」という結論は、出ていません。
しかし、オンラインコミュニティや自己報告によれば、以下のタイプにADHD傾向がみられやすいことがわかっています。
- N(直観型)+P(知覚型)
- E(外向型)+P(知覚型)
これらを統合すると、E+N+Pが組み合わさったタイプに、ADHDっぽい性格や行動がみられるようです。
E+N+Pまで絞ることができれば、挙げられるMBTIは2つ。
ENFPとENTPです。
もしくは、上記のMBTIと似た傾向を持つESTPなども挙げられるでしょう。
これらのタイプは、常に外部からの刺激を求め、テンションが高いという共通点があります。
頭の中でアイデアが止まらなかったり、すぐ行動に移したくなすという傾向があるため、ADHDっぽい行動が目立ちやすいのです。
しかしここで重要なのは、そのように見えることがあるだけで、必ずADHDをもつという意味ではないことです。
MBTIとADHDは別の枠組みであり、MBTIタイプだけで医学的な判断を下すことはできません。
しかし、自分のタイプとそれに基づく性格特性を知ることで、自分が特定の行動に出る理由や、楽に生きられる方法を見つけるヒントになるでしょう。
E(外向型)× ADHDの傾向を活かすために
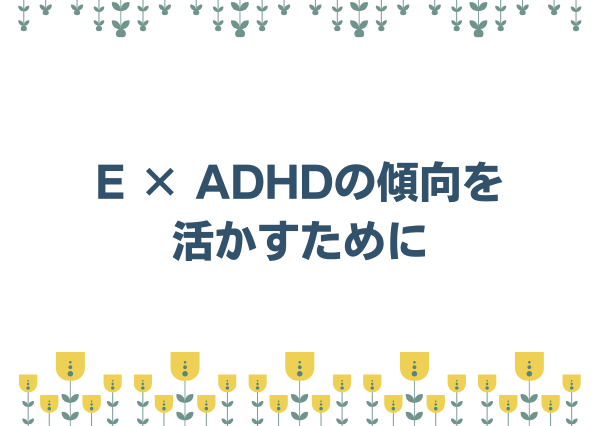
E(外向型)で落ち着かないと感じる人、行動するのが止まらないと感じる人におすすめの、環境づくりや習慣のヒントを3つご紹介します。
エネルギーをチーム活性化のために使う
E(外向型)×ADHD傾向の人は、場の空気を読むよりも「盛り上げる側」に回ることが得意です。
周囲のモチベーションを引き出す力があるので、営業・イベント運営・広報など、人との関わりが多い場で活躍できるでしょう。
自分のテンションを無理に抑えるのではなく、周囲の人が話しやすくなる雰囲気づくりに使うことで、エネルギーをポジティブな方向に転換できます。

E(外向型)は周囲の空気を読んで適切な行動をしたり、特にコミュニケーションに活かすことが得意とされていますが、必ずしも全員がそうではありません。
「明るいけど空気を読むのは苦手」
「コミュニケーションは好きだけどたまに的外れなことを言ってしまう」
そんなお悩みを持っていたら、苦手な部分を克服するのではなく、得意分野を伸ばすことに注力してみる方法もありますよ。
瞬発力をブレストで活かす
ADHD的な「発想の飛躍」や「直感的なひらめき」は、E(外向型)との掛け合わせで、より強力になります。
ひとりで考えるよりも、人との会話の中でアイデアが次々に生まれるのが特徴でしょう。
そのようなタイプの人は、ブレインストーミングやディスカッションの場で積極的に発言しましょう。
自分の発想やひらめきを「脳内が忙しい」「落ち着かない」と考えるのではなく、高い創造性として活かせます。
大事なのは、思いついたことを記録する習慣をつけることです。
勢いに任せるだけではすぐ忘れてしまい、むしろもったいないことに。
散らかった考えを、あとで整理できるようにすると、さらに成果につながるでしょう。
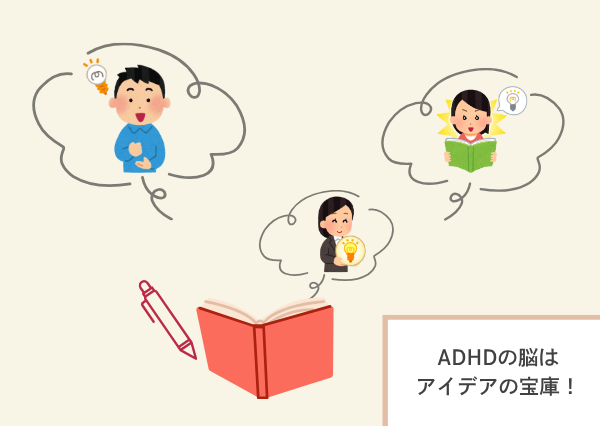
衝動性を行動力という強みに変える
E(外向型)× ADHD傾向の人は、行動力に長けているともいえます。
脳内が忙しいN(直観型)タイプもADHDと似た部分を持ちますが、身体的な落ち着きのなさを自覚している人は、ぜひその行動力を活かしてみてください。
行動力に長けている人は失敗も多いですが、チャンスを逃さないという大きな武器にもなります。

完璧を求めすぎず、とりあえずやってみて学ぶというサイクルを意識すれば、失敗が経験値に変わるでしょう。
衝動的に見える行動も、目的意識を持つだけで「スピードと行動力の人」として評価されるようになります。
E(外向型)=ADHDは大きな誤解!
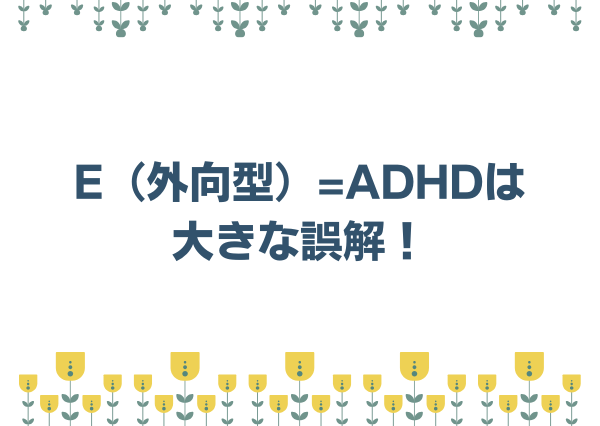
このテーマでは、E(外向型)=ADHDという誤解をされやすいですよね。
E(外向型)=ADHDという極端な認識ではなくとも、E(外向型)の人はADHDになりやすいという考え方もまた、避けるべきでしょう。
確かに傾向として重なりやすいですが、診断対象となるほどではない人も多数います。
MBTIは性格傾向のツールであり、ADHDは診断名を伴う医学的状態です。
自己診断や、軽率な結びつけには注意が必要です。
そしてもうひとつ。
自分が落ち着かない性格だったり、集中できないという悩みがあったりすることで「ADHDかも」という短絡的な思い込みをすることも注意しましょう。
実際には、睡眠不足・ストレス・仕事のミスマッチなどでも、ADHDのような症状があらわれることはあります。
昨今、芸能人やYoutuberがADHDを公表することが増え、落ち着きがないだけでADHDだと思い込む人もいるでしょう。
自己診断が一番危険ですから、どうしても気になるようなら医療機関を受診してみると良いでしょう。
E(外向型)はADHDになりやすい?
E(外向型)が、必ずADHDというわけではありません。
E(外向型)は行動的・社交的という特性を持つため、ADHDの動き回りたい特性や刺激を欲する部分と似て見えるだけ。
実際、ADHDという発達障害は、多様なタイプで報告されています。
落ち着かなかったり、何かしていないと気が済まないという性格だけで、診断できるものではないのです。
さらに、MBTIとの明確な因果関係は確認されていません。
「EタイプがADHDっぽい」は悪い意味?
E(外向型)は明るく陽気なイメージを持ちますが、ADHDは「発達障害」というイメージが強く、ネガティブな印象を抱かれることも多くありますよね。
しかし、落ち着きがなかったり飽きっぽかったりすることは、必ずしも悪いことではありません。
E(外向型)× ADHDっぽさは、創造性・即応性・行動力という強みにもつながります。
大事なのは、なぜそのような行動に出るのかを知り、それが活きる環境や習慣を作ることです。
E(外向型)は、ルーティンワークが多かったり孤独だったりする環境は苦手です。
ADHDも同じように、合わない環境では本領を発揮しづらいのです。

大事なのは「自分を知ること」
この記事は、E(外向型)にADHDが多いのかについて解説していますが、大事なのは
E(外向型)にADHDが多いの?
ということではありません。
なぜE(外向型)にADHDが多いのか、強みとなる部分は何なのか、どのような環境で生き生きできるのか。
そんなふうに、当人が生きやすくなるためのヒントを得ることが、なによりも大切です。
E(外向型)で「常に刺激が欲しい」「落ち着かない」と感じたとき「ADHDだったらどうしよう…」と考えるのではなく、自分を知ることを意識しましょう。
周囲のペースに合わせるのではなく
を観察して、自分に合った静と動のバランスを整えること。
それこそが、外向 × ADHDっぽさをポジティブに活かす第一歩になるでしょう。
まとめ
もしあなたがE(外向型)で、ADHDっぽさを感じることがあるなら、それをヒントに自分を理解する強みに変えましょう。
大切なのは、ADHDっぽさを弱さとして捉えず、自分の質として理解することです。
MBTIのE(外向型)という指標を使って、自分がどう動いたら楽しいか、どう休むのが心地いいのかを探してみましょう。
E(外向型)でエネルギッシュなあなたならではの強みを、磨いていけるはずです。