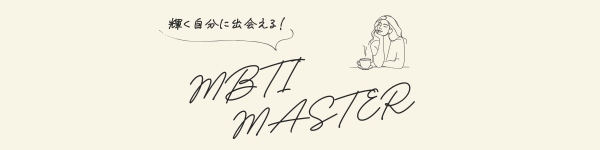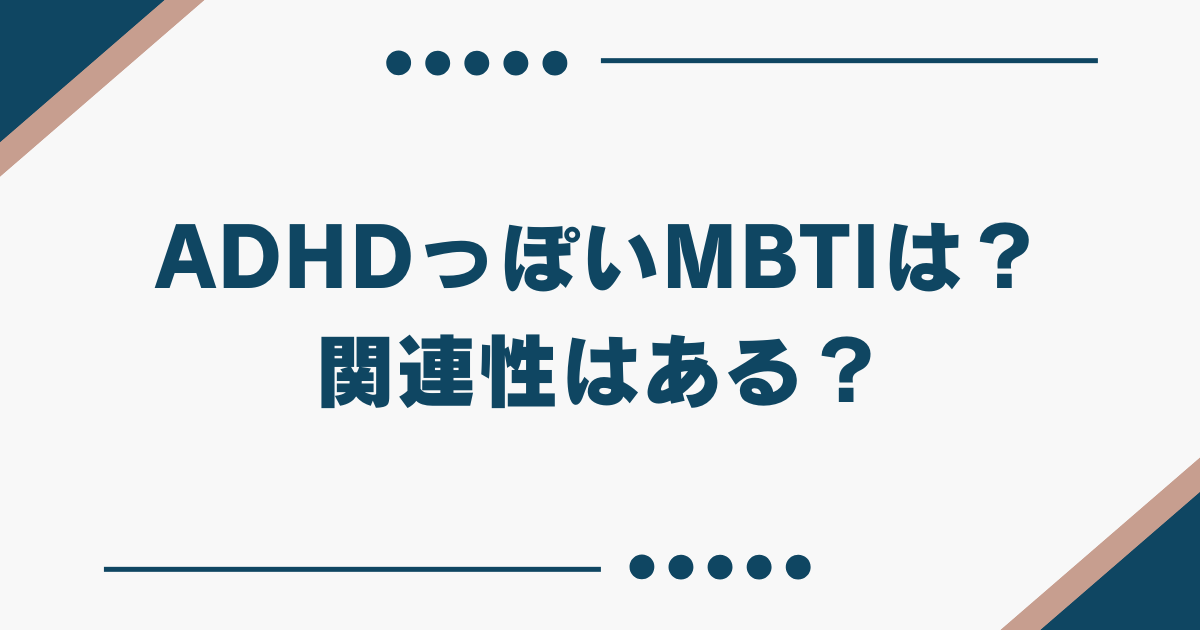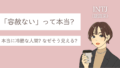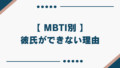「なんで自分は集中力が続かないんだろう」
「なんでこんなに飽きっぽいんだろう?」
ご自身の性格について、そう思ったことはありませんか?
もしかしたらそれは、あなたがADHDっぽいMBTIだからかもしれません。
「ADHDっぽさ」と、性格傾向として知られる MBTIは一見似ています。
この記事では、MBTIとADHDがどのように似て見えて、そしてどう違うのかを解説します。
大切なのは、MBTIもADHDもあなたを責めるものではなく、自分を理解するためのツールだということです。
焦らず、少しずつ自分のクセを紐解いていきましょう!
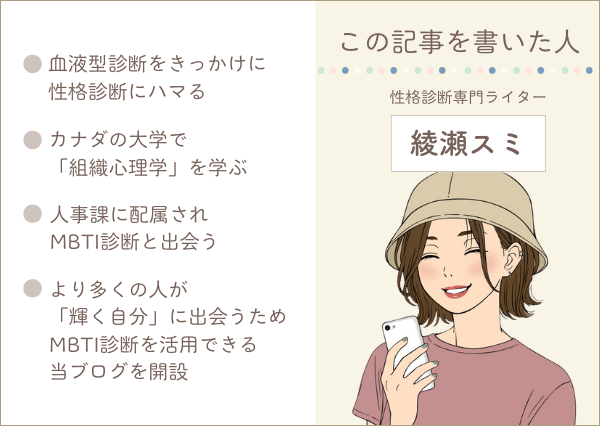
まずはADHDの特徴からおさらい
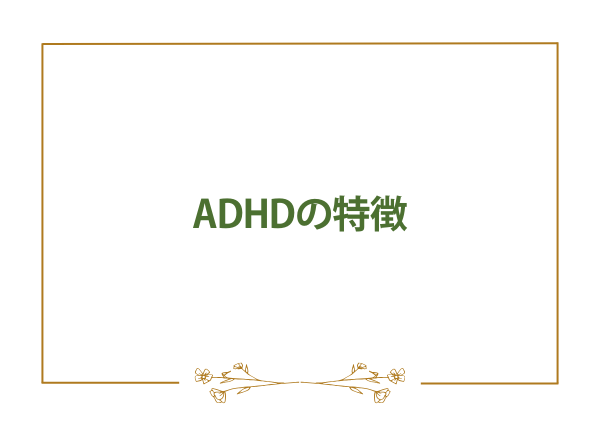
まずは、ADHDとは何かを軽くおさらいしておきましょう。
ADHDは、最近芸能人が公表することが増え、知られるようになった発達障害の一種です。
主な特性は、不注意・多動性・衝動性の3つ。
以下にてより具体的に解説していき、その次に、ADHDの特性に当てはまりやすいMBTIをご紹介します。
不注意
ADHDの特性の1つは、不注意です。
興味のあることには強く集中できるのに、関心が薄いことや単調な作業(ルーティン)になると注意力が散漫になります。
ケアレスミスをしたり、指示を聞き漏らしたりして、失敗が多くなりがち。
また、外部からの音や光など、ちょっとした刺激にも気がそれやすく、マルチタスクが苦手な傾向があります。
本人は「やる気はあるのになぜか集中できない」と感じ、結果的に自信をなくすことにつながるケースも。
また、忘れものが多かったり約束を忘れてしまったりすることもあります。
多動性
ADHDの多動性は、特に子どもの頃に出現しやすい特徴です。
しかし、大人になってもかたちを変えて続くことがあります。
たとえば常に手や足を動かしていたり、じっと座っていられずに貧乏ゆすりをしてしまったりする人は、ADHDの特性である可能性があるでしょう。
多動性は上記のようにからだの動きだけでなく、精神的な多動もあります。
たとえば、頭の中に次々と考えが浮かんで「常に何かをしていないと落ち着かない」という感覚がある人は、ADHDの可能性があるでしょう。
また、退屈が苦手で、新しい刺激や変化を求めるエネルギッシュさも、ADHDの多動性の一種かもしれません。
衝動性
ADHDの衝動性は、思いついたことをすぐ口に出してしまったり、感情が先に出て行動してしまう特徴です。
たとえば、会話中に相手の話を最後まで聞けずに割り込んだり、衝動買いをしたりすることをいいます。
感情の起伏が激しく、怒りや焦り、不安をコントロールしにくい傾向もみられるでしょう。
この特性においても、本人に悪気はなく、むしろ「気づいたら動いていた」というケースが多いのが特徴です。
ADHDっぽいMBTIはある?
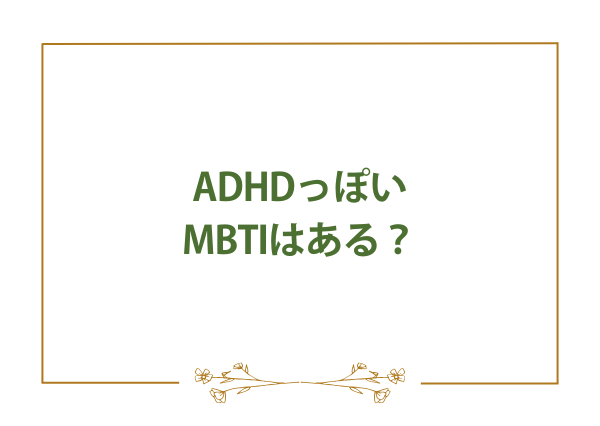
MBTIは性格傾向を示す道具で、医学的な診断ではありません。
ADHDは「注意が散りやすい」「衝動的に行動する」「計画性がない」などの特徴を持ちます。
実は、ADHDっぽいMBTIを大きく分けると、N(直観型)とP(知覚型)に該当することがわかりました。
実際、MBTI公式のガイドラインでも「ADHD傾向のある人には、直観/知覚(N + P)型が比較的多く見られた」という調査結果が示されています。
とはいえ、これらのタイプ=ADHDという単純な図式ではなく、あくまでも傾向が似ているということだと理解しましょう。
N型の人
MBTIで「N(直観型)」が強い人は、情報をひらめきや可能性でとらえる傾向があります。
そのため、手順を守ったり細かい確認をしたりするのが苦手で、ADHDの不注意に似た特性を見せることがあります。
また、N(直観型)は頭の中で常に複数のアイデアが動いており、ひとつの作業に集中しても、途中で別の発想に飛び移ってしまうこともしばしば。
現実で起こっていることよりも、理想や未来のビジョンを重視するため、今やるべきことが後回しになりがち。
こういった点も、ADHDの不注意に似た特徴といえますね。
本人は決して怠けているわけではなく、新しい刺激を求める脳の動きが活発すぎるのが原因です。
また、上記のN(直観型)の特徴に当てはまる=ADHDの可能性が高い、ということではありません。
あくまでADHDの不注意と、N(直観型)の特性が似ているというだけですので、参考までに。
P型の人
「P(知覚型)」は、柔軟さと自由を重視するタイプです。
変化には強いのですが、スケジュール管理や締め切りなどのルールや規則にストレスを感じやすい傾向があります。
この特性が、ADHDの多動性や不注意に似て見えることがあります。
P型は思いついたときに動くことが得意で、気分や環境によって行動が変わります。
そのため、タスクの優先順位を立てるのが苦手なのです。
また、興味のあることには驚異的な集中を見せる反面、飽きた瞬間に切り替えるため、結果的に整理整頓されていないような印象になりやすいでしょう。
ADHDっぽい特徴を強みに変えよう!
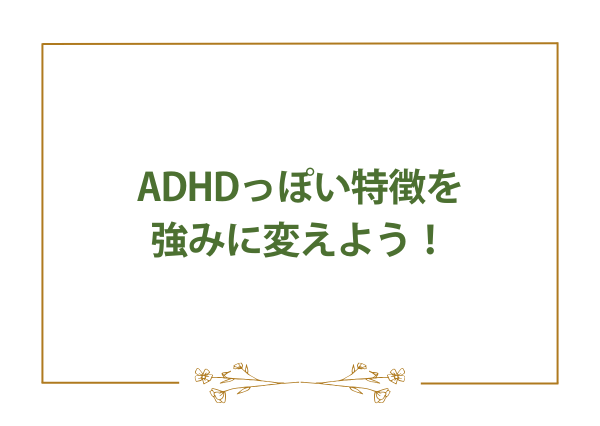
「飽きっぽい」「ルールが苦手」「頭の中が忙しい」
ADHDの特徴でもあるこれらは、欠点ではなくN+P型の才能の種ともいえるでしょう。
たとえば、仕事だったらクリエイティブなプロジェクトや新規事業など、斬新なアイデアが求められる環境でその才能が開花されます。
メディアやITなどの変化が早い業界では、アイデアを次々に出して柔軟に動ける人材が求められます。
実際、ADHD傾向のある人が起業やクリエイティブ分野で成果を出した例も、多くあるんですよ。
参考:PMC
必ずしもルールを守ることではなく、自分のリズムを知ることが、ADHDっぽさを強みに変える秘訣です。
そして、MBTIを通して「どんな環境なら生きやすい?」「自分のペースをどう設計する?」を言語化したり、具体的にプランニングしたりすると、自信が生まれるでしょう。
脳内の忙しさを強みに変えるには
脳内が忙しいN(直観型)は、アイデアの泉のように、常に新しい発想を生み出します。
その反面、現実的な実行力が追いつかないことが課題です。
このタイプが強みを発揮するには、ひらめきを形にする習慣をつけること。
たとえば、以下のことを意識してみてはいかがでしょうか。
N型の脳は、過去でも現在でもなく未来に生きています。
その発想力を逃さず、具体的な行動に落とし込むサイクルを作ることで、才能あふれるひらめきを形にできるスキルも身につくでしょう。
ひらめくことも、それを実行することも、簡単にできるものではありません。
まさに脳内が忙しいN(直観型)ならではの強みとなるでしょう!
飽きっぽさを強みに変えるには
P(知覚型)は変化に強く、環境の流れを読むのが得意です。
ですが、気分で行動しがちなため「なにごとも続かない…」と感じやすいかもしれません。
このタイプの強みは、即応力にすぐれていることです。
つまり、ほかの人が戸惑う状況でも、瞬時に対応できる能力があるのです。
そんなP(知覚型)が意識できるのは、以下のことです。
P(知覚型)はもともとルールに合わせるのが苦痛に感じるタイプなので、自分が動ける環境を整えるほうがうまくいきます。
ADHDの多動性に似た行動の速さを、逆に活かしていけばよいのです。
変化の時代に最も強いタイプへと進化できるでしょう。
ADHDっぽいと感じたら意識したいこと
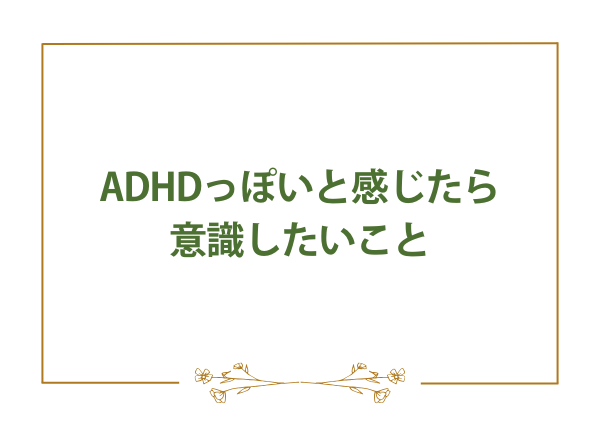
「自分、ADHDっぽいかも」と感じたら、まずは以下を意識してみましょう。
苦手より得意に注目する
ADHD傾向の人は、飽きっぽかったり集中が続かなかったりして、それらを苦手だと感じやすいですよね。
しかし、あくまでそれは関心のないことに対してです。
逆に、興味のあることには驚くほど集中できるのがADHDっぽさでもあります。

興味のないことはやりたがらないけど、興味のあることはどんどん伸ばせる!
これはADHD(っぽさ)ならではの能力でもありますよね
そこで、ADHDっぽさを感じたら「自分が続けられたこと」や「夢中になれた瞬間」を、メモしてみましょう。
それがあなたの得意分野です。
つらい思いをして苦手を直すより、得意分野を増やしたり伸ばしたりするほうが、結果的にうまくいくでしょう。
そのためには、常にスマホにメモできるようにしておいたり、書くのが好きな人はノートを持ち歩いたりするのがおすすめ。
「これ、自分の得意分野かも!」
と思ったら、すぐにメモできる状態にできると良いですね。
環境を味方にする
集中力や感情をコントロールするのが難しいのも、ADHDっぽさの1つですよね。
そう感じたら、自分の意志ではなく環境を調整するのがコツです。
たとえば、集中したい時間にはスマホを別の部屋に置いたり、タイマーで作業を区切って休憩を挟んだりしてみましょう。
また、自宅ではなく静かなカフェで仕事をするなど、場所を変えてみるのも良いですね。
環境を変えるだけで、その後の成果が大きく変わるかもしれません。
努力をするのがつらいと感じたら、視点を変えて「仕組みづくり」を意識しましょう。
自分を実験対象として見る
自分の性格的特徴に疑問を持ったり「ADHDっぽいかも」と感じたら、いっそ自分を実験対象として見てみるのも手です。
自分を分析するのは、決してネガティブなことではありません。
「どうすれば集中できるかな?」「どんな時に気分が上がるんだろう?」と、まるで実験のように自分を観察してみてください。
うまくいかない日もあるでしょう。
そういう日は「失敗」ではなく「貴重なデータが収集できた日」です。
この考え方に切り替えるだけで「なんでできないんだろう…」という自己否定が減り、自己理解が深まります。
自分のペースを守る
他人と比べると「どうして自分は普通にできないんだろう」と落ち込むことがあるでしょう。
しかし、ADHDっぽい人の多くは、発想力・行動力・直感力などにおいて、普通じゃない良さを持っているんです。
まわりに合わせるよりも、自分のテンポで動ける生き方を選ぶほうが、長期的に見て幸福度が上がるでしょう。

たとえば、多動傾向のあるADHDっぽさだったら、複数のことを一度にできる仕組みを作るのも良いですね。
無心で掃除しながら英語のリスニングをしたり、暗記したものを復唱しながら皿洗いをしたり…
電車通勤の時間を使って、スマホに溜めてある自分のアイデアを整理するのも効率的です。

飽きやすいADHDっぽさだったら「小さなタスク→すぐ終わる→報酬GET」という循環を作ってみるのも手です。
小さなタスクを設定することで、完了させるハードルを下げ、すぐ報酬にありつけるという短期集中型の仕組みができあがります。
こうすることで、飽きっぽくてなかなかやるべきことができない人も、少しずつまわりを片付けられるようになるかもしれません。
まとめ
「MBTI × ADHDっぽい」という組み合わせで大事なのは、責める視点ではなく理解しようとする視点。
自分や誰かの思考や行動が、なぜそうなっているのかを知ることが、生きづらさを軽くする第一歩です。
もし「N+P型で、たしかにいろいろと散らかり気味かも…」とピンときたら、MBTIを使って、自分にあったリズムや環境を整えてみてください。
そこに新しい強みが見えてくるでしょう。