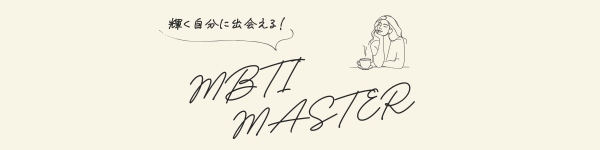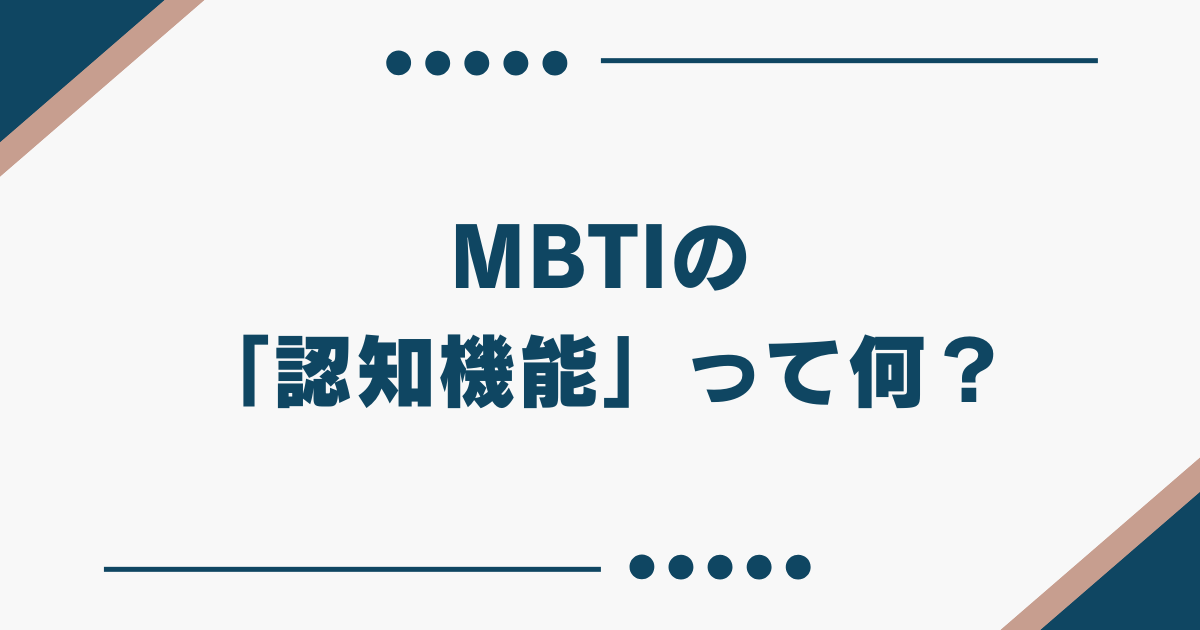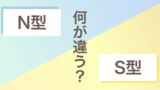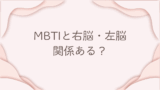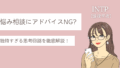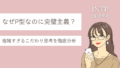MBTI診断では、E/I・N/S・F/T・J/Pという指標がよく知られていますよね。
しかし、より深く理解するためには「認知機能」についても知っておくと良いかもしれません。
この記事では、MBTIの「主機能」「副機能」「劣等機能」という3つについて、わかりやすく解説します。
それぞれの意味や、どのように機能しているのか、性格にどんな影響があるのかを理解し、MBTIについてより深く知ってみましょう!
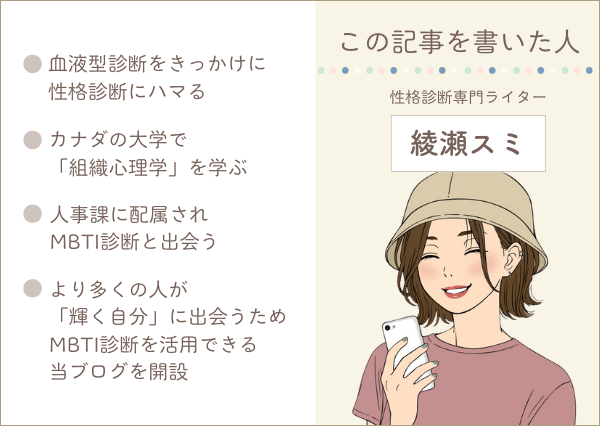
MBTIの認知機能とは?
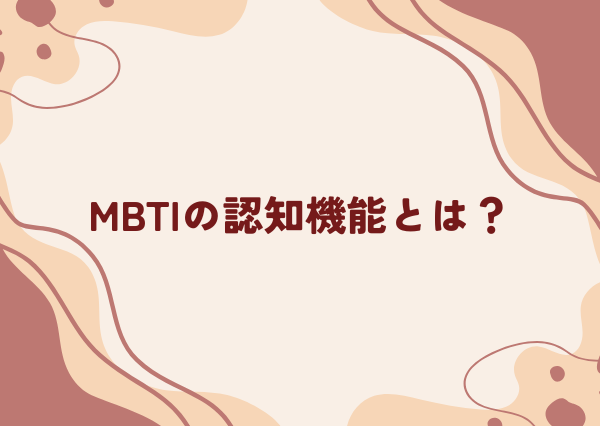
認知機能とは、わたしたちが世界をどう認識し、どう判断するかを決める心理的なプロセスです。
MBTIでは、以下8つの認知機能をベースに、16タイプが構成されています。
- 外向的感覚(Se)
- 内向的感覚(Si)
- 外向的直感(Ne)
- 内向的直感(Ni)
- 外向的思考(Te)
- 内向的思考(Ti)
- 外向的感情(Fe)
- 内向的感情(Fi)
外向的・内向的の2種類と、それぞれに「感覚」「直感」「思考」「感情」という項目があります。
MBTIのアルファベットの組み合わせは、この認知機能をもとに構成されているんです。
では、全8タイプの認知機能を1つずつ見てみましょう。
外向的感覚(Se):五感で生きるリアリスト
外向的感覚(Se)は、五感で生きるリアリスト(現実主義者)です。
Seなので、MBTIにSのつく以下のタイプにみられる機能です。
今この瞬間に起きている現実をダイレクトに捉える機能で、視覚・聴覚・体感など、五感をフル活用して環境に反応します。
「今、何が目の前にある?」
「どんな感触か?動きか?」
という、肌で感じられる体験に強く、スポーツや身体表現を得意とします。
観察力があり、即行動に移せるアクティブさが強みです。
内向的感覚(Si):賢く堅実な安定主義者
内向的感覚(Si)は、賢く堅実な安定主義者です。
こちらもSiということで、MBTIにSのつく以下のタイプにみられる機能です。
過去の経験・記憶・蓄積されたデータをもとに判断する機能で、安定性や信頼性のある情報を重んじます。
「これは以前と同じか?」
「記憶と照らし合わせてみよう」
ルーティンやマニュアル、習慣などを参考に、慎重で安定した判断をするのが特徴です。
外向的直感(Ne):ひらめき飛ばす発明家
外向的直感(Ne)は、ひらめき飛ばす発明家です。
Neなので、MBTIにNのつく以下のタイプにみられる機能です。
ひとつの事象から多様な可能性を、次々と連想していく機能です。
アイデアや発想力、点と点をつなぐ考えが得意なタイプです。
「これは他にどんな意味を持つだろう?」
「もしこうだったら?」
発想が豊かですが飽きっぽく、柔軟な思考と革新性に満ちています。
内向的直感(Ni):未来を読む静かな預言者
内向的直感(Ni)は、未来を読む静かな預言者です。
Niなので、MBTIにNのつく以下のタイプが持つ機能です。
目に見えない本質・パターン・未来の可能性を静かに洞察する機能です。
無意識の中、じっくり熟成された直観に従って動きます。
「この流れの先にあるものは?」
「見えていない真意は何?」
発言や行動は少なくても、深く先を読む直感力に優れたタイプでしょう。
外向的思考(Te):合理性の司令塔
外向的思考(Te)は、合理性の司令塔です。
Teなので、MBTIにTのつく以下のタイプが該当します。
客観的な事実やデータに基づいて、効率的にものごとを判断する機能。
結果・目標・合理性を重視し、ものごとを「どう動かすか」を考えます。
「ルールはどうなってる?」
「目標に最短でたどり着くにはどうする?」
感情よりも成果や生産性に価値を置き、思考の司令塔となってあらゆるものを先導します。
内向的思考(Ti):理屈で世界を組み立てる
内向的思考(Ti)は、理屈で世界を組み立てる機能です。
こちらもTiなので、MBTIにTのつく以下のタイプが該当します。
内側で論理構造を構築し、自分なりの理屈でものごとを理解しようとします。
情報を自分の中に取り込み、一貫性あるシステムとして整理する傾向があります。
「これは理屈として合っているか?」
「なぜ?どうして?」
理論や仕組みを深く掘り下げる探究心・論理力が強いタイプです。
外向的感情(Fe):心優しきムードメーカー
外向的感情(Fe)は、心優しきムードメーカーです。
Feなので、MBTIにFのつく以下のタイプにみられる機能です。
他者の感情やその場の空気、人間関係の調和を優先して行動する機能で、共感力が高く、周囲のニーズに敏感です。
「相手はどう感じている?」
「場の雰囲気に適している?」
礼儀や社会的マナー、人の気持ちを考えた対人コミュニケーションを得意としています。
内向的感情(Fi):本音と信念で生きる
内向的感情(Fi)は、本音と信念で生きることを意味しています。
Fiなので、MBTIにFのつく以下のタイプに備わっている機能です。
自分自身の価値観・信念を最も大切にする機能で、「自分の中で本当に正しいと感じるか」で判断する傾向があります。
「私はどう感じている?」
「これは自分が望んだことか?」
独自の正義感・美意識を持ち、内面的な一貫性にこだわるタイプです。
全MBTIタイプの機能を一覧表でまとめ
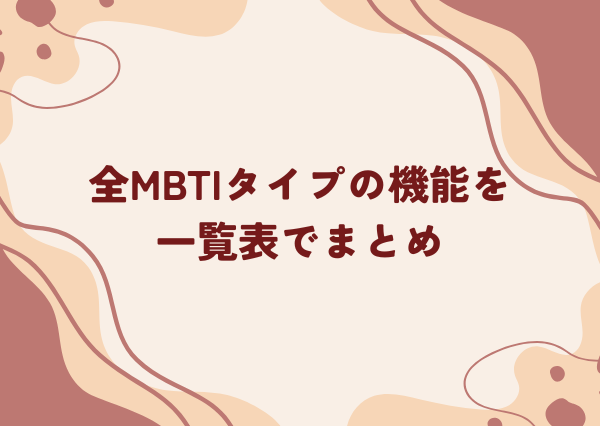
それでは、全MBTIタイプの機能を一覧表でまとめてみましょう。
「主機能」はもっとも強くはたらく機能であり、副機能は主機能の次に強い機能、そして劣等機能はもっとも苦手とする機能です。
| タイプ | 主機能 | 副機能 | 劣等機能 |
|---|---|---|---|
| ISTJ | Si | Te | Ne |
| ISFJ | Si | Fe | Ne |
| INFJ | Ni | Fe | Se |
| INTJ | Ni | Te | Se |
| ISTP | Ti | Se | Fe |
| ISFP | Fi | Se | Te |
| INFP | Fi | Ne | Te |
| INTP | Ti | Ne | Fe |
| ESTP | Se | Ti | Ni |
| ESFP | Se | Fi | Ni |
| ENFP | Ne | Fi | Si |
| ENTP | Ne | Ti | Si |
| ESTJ | Te | Si | Fi |
| ESFJ | Fe | Si | Ti |
| ENFJ | Fe | Ni | Ti |
| ENTJ | Te | Ni | Fi |
MBTIの「主機能」とは?
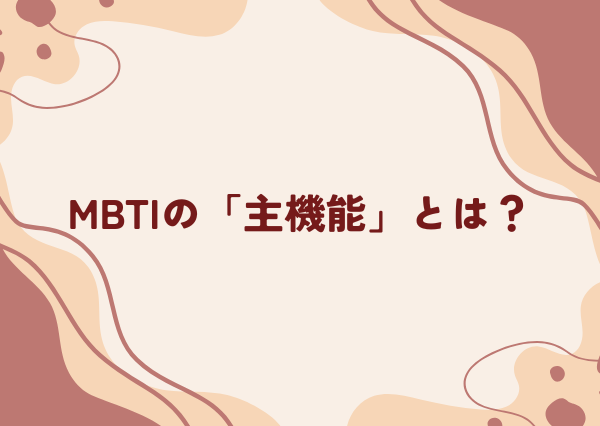
では、MBTIの「主機能」から順に見ていきましょう。
主機能とは、あなたの性格の中心部分となる認知機能です。
人生を通じて最も自然に、無意識に使っている思考パターンであり、あなたの価値観や得意なこと、行動パターンに深く関わっています。
次の特徴があるといわれていますよ。
全MBTIタイプの主機能を一覧表でまとめ
それでは、全MBTIタイプの主機能をまとめてみましょう。
| MBTIタイプ | 主機能 | 簡単な特徴 |
|---|---|---|
| ISTJ | Si(内向的感覚) | 経験とルールを重んじる現実派 |
| ISFJ | Si(内向的感覚) | 過去の記憶と他人への配慮に優れる |
| INFJ | Ni(内向的直感) | 未来を読む洞察力と理想主義 |
| INTJ | Ni(内向的直感) | 長期戦略とビジョンに強い |
| ISTP | Ti(内向的思考) | 論理的かつ即応力に優れた観察者 |
| ISFP | Fi(内向的感情) | 内なる価値観を重視するアーティスト肌 |
| INFP | Fi(内向的感情) | 自分の信念と理想を大切にする夢想家 |
| INTP | Ti(内向的思考) | アイデアと理論を探究する論理家 |
| ESTP | Se(外向的感覚) | 今この瞬間に強く生きる行動派 |
| ESFP | Se(外向的感覚) | 感覚と楽しさを重視するエンターテイナー |
| ENFP | Ne(外向的直感) | 新しい発想に飛びつく冒険家 |
| ENTP | Ne(外向的直感) | 発明・議論を愛する知的チャレンジャー |
| ESTJ | Te(外向的思考) | 効率・組織力重視の実務家 |
| ESFJ | Fe(外向的感情) | 人の気持ちを大切にする世話好き |
| ENFJ | Fe(外向的感情) | 周囲の幸福を考えるリーダータイプ |
| ENTJ | Te(外向的思考) | 戦略的なリーダーシップを発揮する指揮官 |
主機能を理解するメリット
主機能を理解することで、自分の強みや行動傾向を客観的に知ることができます。
また、自分の行動によって起こりうるトラブルや、他者とのすれ違いの原因に気付くきっかけにもなるでしょう。
MBTIの理解を深めるなら、タイプ名だけでなく主機能が何かを知ることが、自己理解と対人関係のカギになることがあります。
MBTIの「副機能」とは?
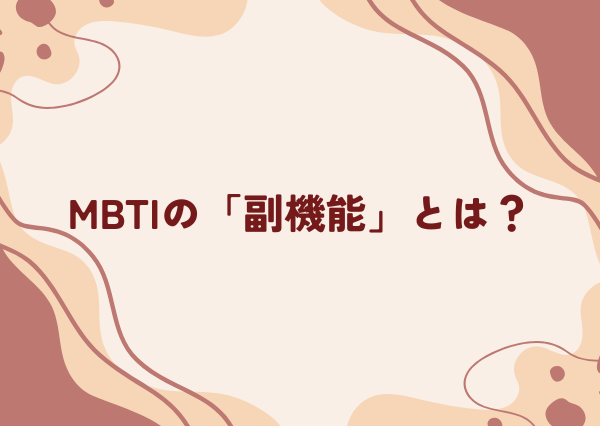
続いて、MBTIの副機能について見ていきましょう。
人は複数の認知機能を組み合わせて行動・判断しているため、主機能だけではMBTIの意味を成しません。
そこで重要になるのが、副機能と劣等機能です。
まずは副機能の役割や、主機能との関係性について解説します。
副機能の役割
副機能は、主機能を補うもう一つの強みです。
通常、主機能が「判断系(思考・感情)」であれば、副機能は「認知系(感覚・直感)」になるなど、バランスをとるように設計されています。
脳診断の記事でもお話していますが、人は偏った機能だけで思考や判断ができません。
右脳・左脳の両方をバランスよく使っているように、認知機能においてもさまざまな種類を組み合わせて、思考が成り立っているのです。
\ 脳診断 × MBTIについてはこちら /
副機能の特徴
副機能には、主機能とは違う特徴があります。
副機能はただ単に「主機能の次に強く出る機能」というだけでなく、後天的に身につくものであるケースが多いようです。
そのため、努力して思考や行動パターンを変えることで、わたしたちは自分のMBTIを変えることもできるんですね!
無意識に出る主機能とは違い、副機能は意識的に使う傾向もみられるため、人によって発達する副機能はさまざまだといえます。
基本的に副機能は、各MBTIごとに定められています(このあと一覧表でご紹介します)。

そうなると、勘の良い方はこんなことを思うのではないでしょうか?
後天的に発達するのに、なぜ最初から「このMBTIの副機能はコレ」と決まっているの…?
そう、後天的に発達するのであれば、発達は人それぞれですから、どの副機能が発達するかわかりませんよね。
では、ENFPを例に挙げて見てみましょう。
ENFPの副機能は「内向的感情(Fi)」です。
では、ENFPの人がもし発達過程で「内向的感情(Fi)」ではない別の機能を使うようになったら…

ENFPなのにENFPの副機能が育たないとなると、矛盾するよね…
そうなんです。
副機能はあらかじめ決まっていますが、ENFPの人の中で必ずしも「内向的感情(Fi)」が発達するわけではありません。
仮にENFPの人が「内向的思考(Ti)」という機能を使うようになった場合、その人のMBTI自体がENFPではない可能性があります。

なるほど!MBTI自体が違うかもしれないんだね
ENFPの人の中で「内向的思考(Ti)」が発達した場合、その人のMBTIはENTPだった可能性があります。
ENTPの副機能が「内向的思考(Ti)」だからです。

ENFPで「内向的思考(Ti)」が発達したら、あなたの中で突然変異が起きているか、そもそもENTPだったか…面白い結果だね!
MBTI診断はもともと明確に分かれた結果ではなく、グラデーションのようになっているので、このようにMBTIをまたいだ結果が出ることも珍しくありません。
副機能は、サブ的なポジションのように見えますが、実はその人のMBTI診断結果を揺るがすくらいの影響力を持った機能なんですね。
全MBTIタイプの副機能を一覧表でまとめ
では、全MBTIタイプの副機能を一覧表で見てみましょう。
| MBTIタイプ | 副機能(セカンダリ機能) | 副機能が与える特徴・影響 |
|---|---|---|
| ISTJ | 外向的思考(Te) | 実務的で合理性を重視し効率化に優れる |
| ISFJ | 外向的感情(Fe) | 周囲への配慮や調和を大切にしよく気が付く |
| INFJ | 外向的感情(Fe) | 人間関係に理想を持ちつつも深く共感する |
| INTJ | 外向的思考(Te) | ビジョンを現実に落とし込み戦略的に動ける |
| ISTP | 外向的感覚(Se) | 瞬発力があり状況判断や実技に長けている |
| ISFP | 外向的感覚(Se) | センスに優れ芸術的な表現や直感的な行動を好む |
| INFP | 外向的直感(Ne) | 発想が自由で可能性を広げるのが得意 |
| INTP | 外向的直感(Ne) | 好奇心が強く新しい視点を発見する |
| ESTP | 内向的思考(Ti) | 自分の論理基準を重視し臨機応変かつ効率的な選択が得意 |
| ESFP | 内向的感情(Fi) | 自分の価値観に忠実で他人に流されずに自然体でいられる |
| ENFP | 内向的感情(Fi) | 明るく社交的だが繊細で自分の信念を大切にする |
| ENTP | 内向的思考(Ti) | 発想は奔放だが裏には独自の論理でアイデアを練る |
| ESTJ | 内向的感覚(Si) | 過去の経験や実績に基づき安定的で確実な判断を好む |
| ESFJ | 内向的感覚(Si) | 慣れた方法を大切にし伝統や秩序に信頼を寄せる |
| ENFJ | 内向的直感(Ni) | 直感的に人の未来や成長を見通し支援しようとする |
| ENTJ | 内向的直感(Ni) | 戦略を長期的視点で描き目標達成に向け構想する |
副機能を理解するメリット
主機能だけでなく副機能も含めて理解することで、自分の表に出やすい部分と支えている内面の両方を認識できます。
またMBTI理論では、健全な成長には「副機能の発達が不可欠」と考えられています。
主機能だけに偏ると視野が狭くなったり、極端な行動に出たりする可能性があるからです。
副機能を意識的に使うことで、より柔軟でバランスのとれた人格に近づけるでしょう。
MBTIの「劣等機能」とは?
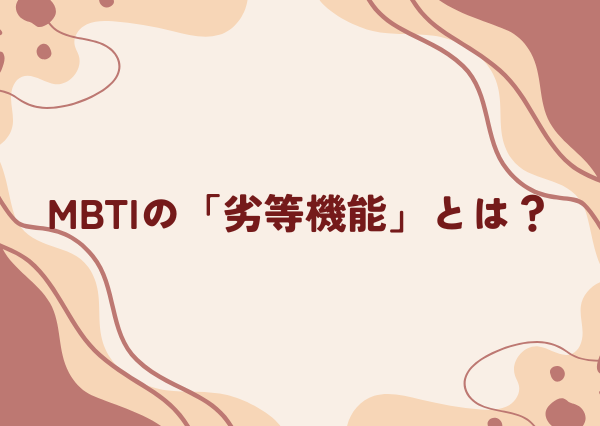
最後に、MBTIの劣等機能について解説します。
劣等機能はその名の通り、各MBTIの中でもっとも弱い機能です。
性格タイプの中で「もっとも苦手な部分」といってもよいですが、それだけの機能ではありません。
劣等機能の役割
劣等機能は、認知機能スタックの中でもっとも発達が遅く、普段は意識されにくい部分です。
しかし、ストレスがかかったときや限界状況で突如現れ「裏の顔」として働くことがあり、自分でも驚くような言動の原因になります。

「劣等機能」と呼ぶくらいだから、機能としては出てこないのかな?と思ったけど、裏の顔として常にスタンバっている機能なんだね…!
劣等機能の特徴
劣等機能は普段は意識されにく無意識下にありますが、ストレス時に暴走しやすい傾向があります。
自己制御が効かなくなることもあり、扱いには注意が必要な機能だそうです。
長期的な自己成長において「統合すべき影の部分」として重要な存在にもなります。
全MBTIの劣等機能を一覧表でまとめ
では、全MBTIの劣等機能を一覧表でまとめてみましょう。
| タイプ | 劣等機能 | 解説 |
|---|---|---|
| ISTJ | 外向的直感(Ne) | 新しい可能性や変化への対応が苦手 |
| ISFJ | 外向的直感(Ne) | 新しい発想や突飛な考えを受け入れるのが苦手 |
| INFJ | 外向的感覚(Se) | 感覚的な刺激に鈍感で即時対応が苦手 |
| INTJ | 外向的感覚(Se) | 五感を使って感じるのが苦手で環境変化にストレスを感じる |
| ISTP | 外向的感情(Fe) | 周囲との調和を意識するのが難しく疲弊する |
| ISFP | 外向的思考(Te) | 効率や論理性を追求しすぎると不安になる |
| INFP | 外向的思考(Te) | 論理や結果を優先しすぎる環境でストレスを感じやすい |
| INTP | 外向的感情(Fe) | 感情表現や共感が難しく周囲と感情的に繋がるのが不安 |
| ESTP | 内向的直感(Ni) | 将来を見通すことが苦手で長期的な視野に自信を持てない |
| ESFP | 内向的直感(Ni) | 抽象的・哲学的な話題や将来のビジョンを抱くのが苦手 |
| ENFP | 内向的思考(Ti) | 論理的思考の整理に苦手意識があり細かい分析ができない |
| ENTP | 内向的感情(Fi) | 自分の内面の価値観や感情を掘り下げるのに不安を感じる |
| ESTJ | 内向的感情(Fi) | 他人の感情や価値観に踏み込みすぎると疲れる |
| ESFJ | 内向的思考(Ti) | 論理的な内省や構造的な分析に不安を感じる |
| ENFJ | 内向的感覚(Si) | 過去の記憶や経験から学ぶのが苦手 |
| ENTJ | 内向的感覚(Si) | 経験からの学びや積み重ねを見逃し過去より未来に注目しすぎる |
劣等機能を理解するメリット
劣等機能を理解することには、自己成長や人間関係の改善において大きなメリットがあります。
その人が最も無意識的に扱う傾向があり、苦手意識を持ちやすい領域。
しかしこの苦手を意識し始めることで、自分の偏りに気づき、視野を広げるきっかけになるかもしれません。
劣等機能はストレス時に過剰に現れやすく、自分でも驚くような行動を取る原因にもなりえます。
そうした反応の理由を知っておくことで、自分の状態を客観的に見つめ、冷静に対処できるようになるでしょう。
つまり、劣等機能は弱点ではなく、成長の余白。
それを受け入れ育てていくことで、より柔軟で成熟した自分に近づけるのです。
まとめ
MBTIにおける「主機能」は、その人の思考・行動パターンの根幹をなす重要な軸です。
主機能だけでなく、副機能や劣等機能とのバランスも理解することで、自分の強みやつまずきやすいポイントがよりクリアになります。
自分の認知機能の組み合わせを知ることは、自己理解を深めるだけでなく、他者との関係をよりスムーズに築くための大きなヒントにもなりますね。
MBTIをただの診断で終わらせず、成長のツールとして活用していきましょう!